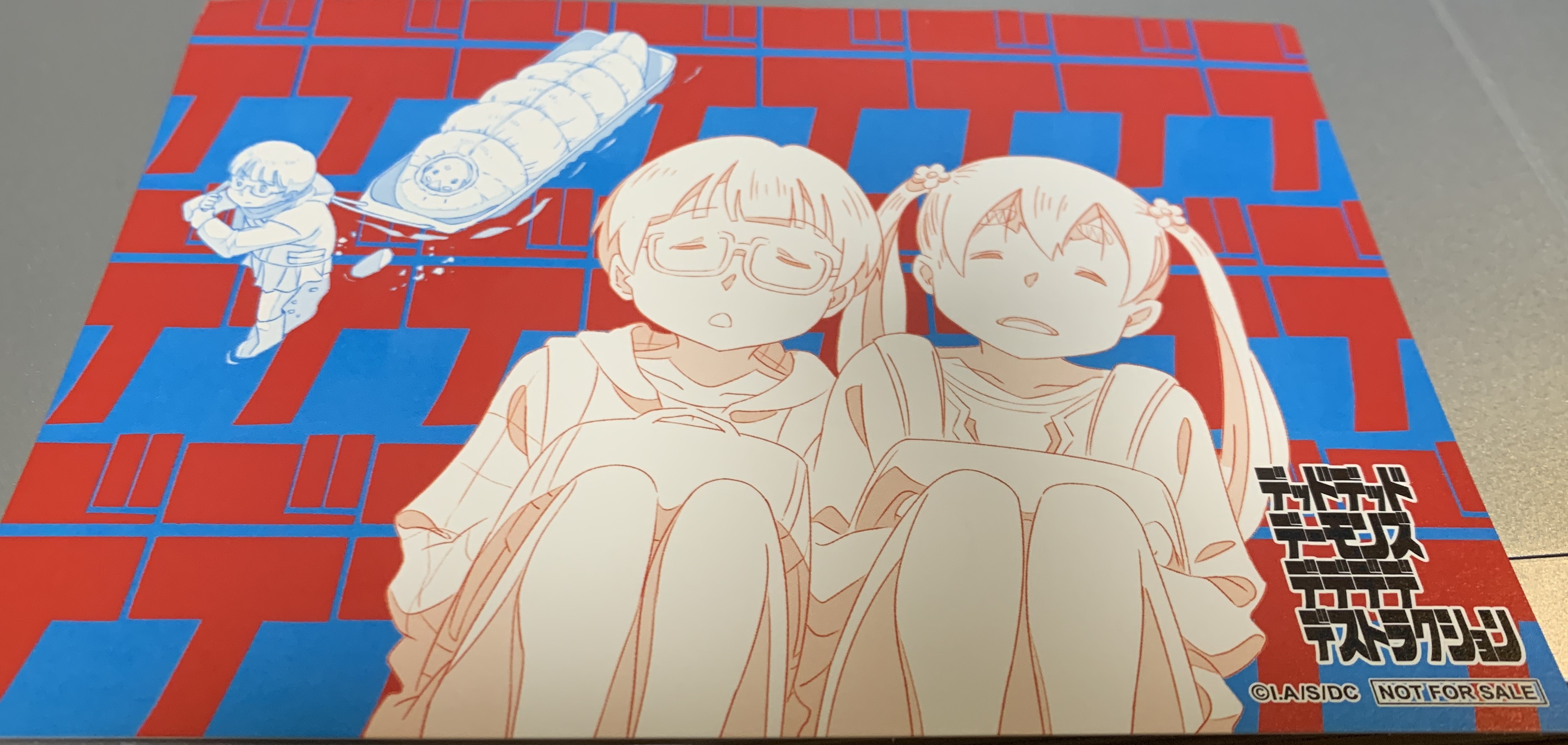デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションを観に行った 4/14
最近映画館に足を運ぶ機会が取れなかったため日曜日を利用して近場の劇場へ行ってきた。視聴した作品は『デデデデ』前情報は劇場に行く前に見た予告版だけで、anoちゃんといくらちゃんが声優をやっている事のみ。予告編と申したが、本編の日常一コマを切り抜いた映像しか見ていなかったため本編でいきなり未確認飛行物体が登場するシーンで唖然とした。中川役のanoちゃんの演技は板についているように思えたし、いくらちゃんの演技も最初は気になったが直ぐに慣れた。本作は、謎の未確認飛行物体が首都圏上空に突如現れ、沖縄から援助に訪れた米軍が新型兵器で爆撃する所から始まる。主人公は以前上空に滞在する5000メートル級の飛行物体が見える都市圏の学校に通っているごく普通の高校生である。話は逸れるが大学の講義でメディアを読み解く授業があり、作品という与えられたデータから独創的な解釈を生み出す事を主目的としており、最近は考察厨への路を歩み出した所だったため本作でも色々考えた。と言いたい所だが私は内容を記憶するのが得意では無いので見返せるオンデマンドタイプでないと細部への考察は行えない。これは、もう一度映画館へ足を運べというお達しなのだろうか。
最初の場面で、主人公の幾田りら演じる門出は、首都圏の一角を丸ごと巻き込んだ大事件でも何も変わらない日常というものにどこか厭世的な気持ちを募らせていた。自分も現実で大地震が起こる際に人々の目に映る期待の様な眼差しを捉えていたので共感できる部分があった。結局、自分に直接影響が無ければ只の日常を少し楽しく変えるだけの空虚なイベントに過ぎないというものだ。最近読んでいる『ゼロ年代の想像力』という書籍で、バブル崩壊以降、社会に対する信用や信頼が低下し、ある種の理不尽さを内面化した人が増えたという指摘があり(こういう時に引用できると良いよね。)それ以降の作品でも社会が提示する大きな物語を信奉する考え方よりも、自分の信じたいものを信じるという価値観のもとで生きる人が大多数を占めるようになった。そんな中で国中を巻き込むほどの災害や事件が発生すれば、それに対して国や国民が一斉に支援を行う、即ち大きな物語が生まれる訳で、そこにはオリンピックやワールドカップと言った国中が同じ方向へ歩ける瞬間が生まれる。これと同じ現象が作中で突如訪れた謎の飛行物体と関連している気がした。そして、そんな歴史の一ページに残るほどの大事件でさえも日常をディストラクションしてくれない事実にどこか絶望に似たものを感じている事を彼女の心情にみた。謎の飛行物体は不安因子の身を社会に蔓延させて自身は何も起こさない。それに対し、政府や民間企業?のいくつかは兵器を開発したり自衛隊を要請し飛行物体から現れた可能性がある生命体をせん滅する事を試みる。世界に登場した謎のアーキテクチャが攻撃的という従来のSF的な認識に囚われずに、ただそこにあるという想像力はスタニスワフ・レムの「ソラリス」などとも共通しているように感じた。人間は自分の理解を超えた存在を恐怖の対象とする習性は今も昔も変わらないのだろう。本作では、性愛と友愛を意識的に分けて描く様子が見て取れた。門出と中川は高校の同級生グループ5人組に所属しており、その中の一人、種崎敦美演じる栗原キホは同級生の小比類巻君に告白して無事その恋は成就する訳だが、その様子をみて中川凰蘭は言葉で詰る訳で、親友である門出が恋する先生との接近に際しても同様の態度を取る。個人的にも昨今の若者は性愛という観点から人付き合いする割合が減っているというか、将来子供を夫婦間で作って円満な生活を営むという将来像に希望を持っていない気がする。以前に、韓国の超少子化問題にフォーカスしたニュース番組でも、自分の様な想いを将来生まれてくる子供にさせたくないという共感性を発揮していた。これはエゴだと思っているけど。後、一般的にスクールカースト上位に君臨する人達は所感として共感能力や配慮の目が鋭い気がする。逆に自分の様なオタクコミュニティに属している人間は、自分の世界で頭がいっぱいで自分に興味が無くて無害な対象にはとことんまでに無関心で、自分に不利益が被られる状況では当たりが強い印象がある。これは狭いコミュニティでの少ないサンプルからの観察で敷衍して一般化する事は出来ないが空気感や雰囲気として感じ取っている部分がある。話が逸れましたが、昨今の社会では性愛よりも友愛を尊重する流れがあり、本作もそれが意識的に描かれているように読み取れた。
謎の浮遊物体に関して、SNSで蔓延る大多数意見への迎合や付和雷同みたいなものも描かれていた。観ていて浮遊物体が何を象徴しているかあんまり分からなかったが、コロナウイルスや巨大地震の様な世間を大きく揺るがせるがそれ自体に悪意や意思が介在しているとはいいがたい何かでは無いかと思った。デデデデが連載されたのは2014年でコロナウイルスを意識して描いたとは思えないが、自分とは直接は関係しないが大きく社会を動かす何かを意図して書かれた事は間違いないし、某流行り病が蔓延した2022年に文化庁メディア芸術祭で受賞した事も偶然ではないと思われる。また、普段マンガ原作の映像作品を視聴しない自分を劇場に駆り立てた本作は、メディアとして社会の潮流と無関係でない事が雰囲気として漂ってくる。エロゲやアニメ等で普段の視聴者層とはかけ離れた層の視聴者がつく作品は大概、何かメッセージ性や周囲を巻き込むだけの引力を備えている。運命論を語っている訳ではなくその作品がそれだけに社会の深層で渦巻く声をエコーさせる拡声器としての装置を担っているということだろう。
浮遊物の不安因子は不確定な情報を生み出し、政府もその声を汲み取り正義を振りかざして攻撃的な態度を取り、歩み寄るという融和の姿勢を見せずにいたりする。これって今の私たちの状況と似ているよねという事を自覚するための装置として機能している本作だが、恐らくそれを目的として描かれている訳ではない事が後半部分で明かされる。先程の性愛と友愛を分けて描かれた際に登場した栗原は、飛行部隊から送り込まれる円盤上の浮遊物の落下に巻き込まれて死亡し、死を悼むがその世界ではコロナウイルスに誰かが感染する程度のインパクトで彼女との交友は色濃く描かれては居たがあまり感傷的な態度になれなかった。これを意図的に描いている点が制作陣の手腕だろう。友愛による関係は儚く脆いが、それでも前を向いて今を生きようと奮起する少女たちが描写されていた。その後、中川のもとに謎の知的生命体が登場し、過去の回想シーンorパラレルワールドの架空の記憶を覗くシーンに入るのだが、それは天真爛漫で少し変わった中川と内気な少女を演じる現在の門出とは大きくかけ離れた幼少時代が描かれる。凰蘭は、内気でイジメられる同級生を傍観する事しか出来ない典型的な小学生で、門出はその名前からデーモンのあだ名をつけられ他の子たちから揶揄われ孤立する訳だが自分の信じたものを頑として捨てない芯のある少女として描かれる。ある日、二人は空に浮かぶUFOを目撃し、誰からも信じられない疎外感を共有し接近する。(信じたいものを信じる的な現代、若しくは旧来的な価値観像を象徴的に描くシーンか?)そのUFOから謎の生命体が登場し二人は少年たちに虐められるソイツを助ける。謎の生命体に少々懐疑的な二人だが、ソイツの秘密道具で意思疎通が可能となり相手が攻撃的な的でない事を知り関係性を深める事となる。ソイツは藤子不二雄のD衛門のように発展した文明からの技術を授け、時には透明マンとや、魔法のステッキを駆使していじめっ子を撃退し小さな世界を変革していく。そして、門出は善を謳い、悪を駆逐する事を信念として行動する事になるのだが、ある日、ふとしたきっかけで魔法のステッキを使って電車を砲撃し脱線事故を誘発する。そこから引き返せなくなった門出は、透明マントと魔法のステッキを用いて、悪人を脅迫し悪人が思う更なる悪人へその歩みを進め殺害を試みる。所謂無敵の人として門出は描かれ、総理大臣を殺害するに至る。最初は、一日一善という我々が共感しやすい正義を掲げる優しい少女として描かれるが次第に踏ん切りがつかなくなり倒錯した正義を掲げ手にした道具で社会を変革する変貌ぶりが描かれる。自分自身、デーモンとあだ名をつけた少年たちを華麗に撃退して一日一善を行う事を条件に許してあげるシーンなんかはなんてほっこりする作品なんだと癒しに似た気分だったのに後から総理をぶち殺したりするシーンで猫ミーム風に言えばhaaだった。これは恐らく正義は主観以外の何ものでもなく正義は存在しないという事実のみが真理を示すものだろう。自分自身が正しいと思う事が他者にとって正しいとは限らないと独善的な態度で暴走する自分自身を省みる必要性を感じ取った。こっから何か重要そうな考えを読み取れそうなのだがあんまり浮かばないのが悲しい。ただ、最近読んでいる「ゼロ年代の想像力」で書かれた思考軸が作品を読み解く際に新たな視点を与えてくれた事は確かだと思う。ただ、それが本当かに対しては以前批判的な態度を貫くべきだと思う。今回は前章で、5月の中旬に後半の章が劇場で楽しめるという事で忘れていなかったら観ようかと思う。多分、マンガが好きな人は須らく知っているのだろうけれど誰かにお勧めしたくなるぐらい面白い作品だった。本当は後続のガンダムSEEDを観に行こうと思ったが思ったよりも重厚な作品で帰っちゃったので機会があればSEEDも観に行こう。